
■播州地方における釣針のはじまり
播州地方における釣針のはじまりは、天保のはじめ頃に加東郡池田村(現小野市池田町)の源右衛門が京都から技法を持ち帰ったとか、多可郡上比延村(現西脇市上比延町)の新兵衛(生田氏)が弘化年間に京都で習得したとか!、最も確かであるのは、加東郡下久米村(現社町下久米)の彦兵衛(小寺氏)が、土佐でその技術を学び帰郷して始めたという説である。
播州地方における釣針のはじまりは、天保のはじめ頃に加東郡池田村(現小野市池田町)の源右衛門が京都から技法を持ち帰ったとか、多可郡上比延村(現西脇市上比延町)の新兵衛(生田氏)が弘化年間に京都で習得したとか!、最も確かであるのは、加東郡下久米村(現社町下久米)の彦兵衛(小寺氏)が、土佐でその技術を学び帰郷して始めたという説である。
確定はできないが、初期のころの釣針の材料は三木の金物の屑や残材が小野に入り、家庭刃物や鎌に使用され、さらにまたその残りが釣針製造に使用されたとある。あまりにも話ができすぎているであろうか。とにかくこの伝承は、これらの金物産地がかなり密接なつながりを持っていたことを示していると思われる。
播州釣針の濫觴は、嘉永4年(1851年)に下久米村の彦兵衛(小寺氏)が土佐よりその技術を持ち帰ったときとされている。しかし、北播磨へ釣針製造の技術が導入されたことについては、まだまだ不明な点が多い。彦兵衛以前にも、天保頃多可郡岡村(現黒田庄町岡)に定右兵衛という釣針師がいて、弘化元年(1844年)頃には上比延村の新兵衛が京都で学んだ鮎懸針の製造を始めたという。また、池田村の源右衛門が天保年間に始めたとも伝える。さらに、多可郡の行商人中島屋卯兵衛の「当座帳」(天保~嘉永)にも、各種の釣針を福地村武兵衛・津万井文三郎・下比延村茂助(いずれも多可郡)から仕入れたとしている。
播州釣針の濫觴は、嘉永4年(1851年)に下久米村の彦兵衛(小寺氏)が土佐よりその技術を持ち帰ったときとされている。しかし、北播磨へ釣針製造の技術が導入されたことについては、まだまだ不明な点が多い。彦兵衛以前にも、天保頃多可郡岡村(現黒田庄町岡)に定右兵衛という釣針師がいて、弘化元年(1844年)頃には上比延村の新兵衛が京都で学んだ鮎懸針の製造を始めたという。また、池田村の源右衛門が天保年間に始めたとも伝える。さらに、多可郡の行商人中島屋卯兵衛の「当座帳」(天保~嘉永)にも、各種の釣針を福地村武兵衛・津万井文三郎・下比延村茂助(いずれも多可郡)から仕入れたとしている。
■技術習得の苦闘と開発(浸炭焼き入れ)
彦兵衛の新しい釣針技術を求めての旅立ちについて諸説がある。『加東郡史』(大正12年刊)は次のように記している。天保13年(1842年)3月、土佐釣針の技法を知ろうと家族と水杯を交わして別れ、土佐の高知に着いた。しかし教えてくれる者がなかったので、偽って四国霊場巡拝者となって数年、釣針職人太田某と知り合い、その下男として住み込んだ。仕えること3年、日夜忠勤を励んだのでその製法を授けられ、奥義を極めることができた。土佐にあること前後10年、その初志を達成して故郷へ帰ってきた。嘉永4年11月のことという。
さらに、小西勝次郎によると、天保元年(1830年)加東郡下久米村庄屋小寺彦兵衛が30歳で土佐へ行き、鍛冶屋高助方で釣針の製造を研究、嘉永4年に帰郷して製造し始めたのが濫觴である。爾来、20数人の門人を養成したので下久米村を中心に他村・他郷に拡がったという。
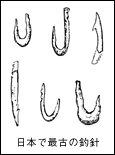
しかし、この地方へ釣針技術をもたらせたのは、彦兵衛系だけでなく、池田村の源右衛門―岸本勘助の系統も考えられる。この地方への釣針は、いろいろな系統のものが導入されたことは確かである。しかしそれらの釣針は「京針」とよばれる遊漁用のものであった。これに満足できなかった彦兵衛は、漁業用の土佐針の技術を習得すべく四国におもむき、苦心して土佐丹吉針の製造法を身につけて帰郷、企業としての釣針の製造に成功したとする。一方特殊技術の伝授をなかなか許可をしてもらえなかったのは、どの地方でもいつの時代でもかわらない。
それこそ苦労に苦労重ねたが奥義まで教えてもらえなかったのだろう。そのため、帰郷して製造を始めたが、肝心の「焼き入れ」のコツがどうしてもつかめず、失敗を重ね続けた。ところが、ふとしたことから下久米村鹿野に住む野鍛冶の指唆で壷の中へ炭を入れて焼いたところ、みごとに成功したという。こうして彦兵衛念願の播州釣針の製造が軌道にのったのであった。職祖彦兵衛の周年と努力は、永久に忘れてはならないのである。
彦兵衛の釣針工程は、次のようなものであったと考えられる。
鉄材を金槌で打って線材を作る→鋏で切る→尖らせる→鑢でイケを起こす→型にはめて手で折り曲げる→尻付け→焼き入れ・焼き戻す。
彦兵衛の釣針工程は、次のようなものであったと考えられる。
鉄材を金槌で打って線材を作る→鋏で切る→尖らせる→鑢でイケを起こす→型にはめて手で折り曲げる→尻付け→焼き入れ・焼き戻す。
■播州地方への広まり
嘉永4年(1851年)に帰郷した彦兵衛は、工夫を重ねつつ釣針の製造に励んだ。彦兵衛の偉大さは、技法を秘密にせず弟子にはもちろん同業者にも公開したことである。これが、北播磨での釣針産業が発展する最大の要因である。『加東郡史』では、「爾来専心斯の発達に留意し、弟子を四方に求めて業を授くるに吝ならさりしかば、その製造忽ちにして遠方に普及し、播磨丹波は勿論丹後三備の地方に拡がれり」(傍点筆者)
つまり広く弟子を募って自分の習得し工夫した技法を公開、快く新式方式を教えたのであった。そのため、彦兵衛から習って釣針職を始めるものが、播磨・丹波は勿論岡山県方面まで広がったというのである。けだし、彦兵衛が釣針製造の職祖と称されるゆえんはここにある。
